目次
宅建まで残り1か月、もう無理だと思っていませんか?
「勉強が進んでいない…」「あと1か月でどうにもならない」
そんな気持ちでこの記事を開いている人は多いと思います。
正直、私も同じでした。過去問は解き切れていないし、暗記も不十分。「今年はもう諦めるしかないか」と思ったこともあります。
ですが、結論から言うと 残り1か月でも合格は十分可能 です。私自身、直前2週間での追い込みで合格を果たしました。
ここでは、私が実際に取り組んだ勉強法や教材、直前期に意識したことを余すことなくお伝えします。
宅建試験は残り1か月でも合格できる理由
合格ラインは約7割でOK、満点は不要
宅建試験の合格ラインは例年50問中35点前後。つまり7割程度を取れば合格できます。
「全範囲を完璧に仕上げる必要はない」という事実をまず押さえましょう。残り1か月なら、得点源になる分野を絞り、効率的に得点を積み上げれば十分合格圏内に届きます。
直前期に伸びやすい科目がある
特に「宅建業法」と「法令上の制限」は、短期間でも得点を伸ばしやすい分野です。出題数も多く、過去問演習を繰り返せば確実に点が取れるようになります。
逆に「民法」は奥が深く、短期集中では伸ばしづらいので最低限に絞るのが得策です。
残り時間が少ないからこそ集中できる
追い込まれた状況は大きな武器にもなります。限られた時間だからこそ、無駄を削ぎ落とし「合格に必要なことだけ」に集中できます。私もこの開き直りが功を奏しました。
私の宅建合格体験記(残り1か月からの逆転するには)
1か月前の正直な状況(不安・焦り)
試験1か月前、受験申込はしてましたがまだ何も勉強していませんでした。正直なところどうせ今からやっても無理だろうしやる気もなくなってるし受けるのやめておこうと思っていた状態でした。そんな状況でたまたま寄った本屋でテキストだけ購入した。 それが受験一か月前の私の状態でした。
(やる気なし状態)実際に取り組んだ勉強法とスケジュール(1か月前~2週間前)
- 平日:仕事の往復の電車内でパラパラとテキストを読むだけ(毎日30分程度)
(ここから急に本気!)実際に取り組んだ勉強法とスケジュール(2週間前~試験本番)
2週間前に急にやる気になりました。今年落ちたらまた来年受けようと思ってしまう。宅建は年一回なので今のチャンスを無駄にするのはもったいないと急にとてつもなく焦りがありました。
- 平日:仕事後に4時間を確保。過去問を中心にアウトプット学習。
- 休日:6時間を確保し、とにかく過去問
- ルール:新しい教材には手を出さず、1冊のテキストと過去問を徹底的に回す。
使った教材(テキスト・過去問・模試)
- 基本テキスト:らくらく宅建塾 [基本テキスト] https://amzn.to/4mqP8IG
- 過去問集権利:過去問宅建塾〔1〕権利関係 https://amzn.to/46tqv8r
- 過去問業法:過去問宅建塾〔2〕宅建業法 https://amzn.to/3VSs1Mi
- 過去問他法令:過去問宅建塾〔3〕法令上の制限 https://amzn.to/47PLuED
上記のシリーズを利用しました
合格当日の手応えと結果
試験本番では手ごたえはなかったです。そりゃそうです 本気になるのが遅すぎでした
しかし結果は34点。その年の合格ラインギリギリで合格できました。
残り1か月で必ずやるべき勉強法
のこり1か月今から間に合わせるための勉強方法についてまとめます。まず2パターンの人に分けて解説します。
パターン1の方:まだ何も手を付けていない人
パターン2の方:テキストは全体的に読み終わってる人
まずパターン1の方はとにかくテキストを2周読んでください。それでパターン2の方に追いつきます。
テキストの読み方(パターン1の方のみ)
1周目:軽く早くとにかく全体を読む。上記で紹介したテキストなら3日で読んでください 3編構成なので1編を1日です。1周目は全体的に把握できればOKです。
2週目:3~4日で読んでください。2週目はハイライトしてある部分(太字や色文字)と数字を中心に見ます。(2週目を読まず即過去問でもいいです 過去問の方が100倍大事です)
読み方の例:1.未成年者の取消権
未成年者は大人に比べて判断能力に欠けるため、自分一人で契約をすると不利な契約をさせられてしまうことがある。たとえば1万円の腕時計を10万円で購入させられるかもしれない。そこで民法は未
成年者が法定代理人の同意を得ずに一人で勝手にした契約は取り消すことができるとした。未成年者がずる賢い大人のターゲットにされないための法律である。
テキストに上記のような解説があった場合は 取り消すことができる この部分だけを見ます。そしてそれを補足するかのようにその前後を見ます。
法定代理人の同意を得ずに一人で勝手にした契約は この部分です。ここまで!
4行ありますが見るのはここまでで十分です。いろいろわかりやすくするために書いてありますが読まなくていいです。なぜなら時間がないからです。今がまだ3か月前なら読みたいです。しかし1か月前です読んでる暇はありません。ということで上の4行の解説では
未成年者が法定代理人の同意を得ずに一人で勝手にした契約は取り消すことができる
ということが読み取れたら十分です。
私の実際の読み方は
「未成年者のことか・・・取り消すことできるとかってのがポイントなんか・・・ふーんなにがやろ・・・(赤字の前後を見て)なるほど法定代理人(ってなんや?まぁええわ)の同意ってのをとらずに未成年者が勝手にしたら取り消せるんか。なるほどふーん」 こんな感じです法定代理人ってわかっていなくても気にしません。誰がいつどうやって取り消すの?と疑問がわきそうですが気にしません。法定代理人という言葉はそのまま試験ででてきますし、誰がいつどうやってなどが試験に必要な知識なら後々に出てくるのでそこで覚えていけばいいです。
ここからパータン1、2の方どちらも過去問を中心
パターン1の方はこの時点で残り3週間ほどです、パターン2の方は1か月残りです。
ここからはとにかく過去問です。過去問にもコツがあります。「出る問題だけに絞る」と「過去問は読み物」と「常識化作戦」です。わからない問題があってもテキストには基本的に戻りません。解説で覚えていきます。(時間がある場合はわからない問題はテキストに戻るのが原則です。ただここでは残り1か月で受かろうとするための勉強法のためテキストには戻らないとします)テキストは時間が空くときに読んでください(電車の中、トイレの中、寝る前など(いわゆるスキマ時間活用))
出る問題だけに絞る
これは簡単です。上記でも少し述べましたが自分の中から湧き上がる疑問の解消は不要です。過去問にあるものを素直にそれだけ解けるようにしてください。また民法で言えば宅建以外の法律系資格の行政書士や司法書士、司法試験などでも試験科目ですがそのような資格の問題集をする必要はないです。宅建合格に求めらえるのは宅建のレベルでいいのです。さらに問題集を2冊3冊と買う必要もありません。1冊を完璧にするほうが自信にも力にもなります。
私の体験談ですが、別の資格試験で過去問を2冊3冊と買ったことがあります。目次構成はどの問題集でもほぼ同じです、そうなると最初の方だけ何度もすることになり後ろの単元ほど弱くなりました。過去問2冊目買いたい場合は1冊を確実の終わらせてからにしてください。
過去問は読み物
問題を解かなくていいです。問題文を読むその時点で【わかる】、【わかるかも】、【わからない】にだいたいすぐ分別できると思います。
わかる:わかるならすぐ解答を読んであっていることを確認してください
わかるかも:ちょっと(10秒ぐらいまで)考えてみてください。そして答えが出ようと出まいとも解説を読んでください
わからない:すぐに解説を読んでください。
上記は肢ごとに行ってください。(1)~(4)のどれが正しいか という問いであっても 肢ごとつまりアイウエの1つづつ問題を読んでは解説を見るを繰り返してください。これが素早く過去問を回すコツです。わからない部分はテキストに戻るという勉強方法があります。王道ですし私も今勉強している資格試験ではそのように行っています。それは時間がある人はそれができますが、1か月で合格するには過去問の問題と解説を覚えていくのが近道です。しかも似たような問題が複数でてくるので繰り返していくとだんだんわかるようになります。
常識化作戦
これは実際に肢毎に問題を見ていくわけですが、この問題はもう当たり前にわかった。私の中では常識だ!と思える肢はチェックを入れます。線で問題を消してもいいです。そして二度とそこは見ません。問題集の全部の肢にチェックが入った、または線で消されれば完璧です。何周も問題を読んでみてどんどん消していくのです。その中でなかなか消えない肢などは苦手な部分です。正攻法ではテキストに戻って確認したりゴロ合わせを作って覚えたり、理由や立法趣旨などからなんとか覚えようとします。ただ1か月前です。そういった自分にどうしても合わない肢や問題は捨てるのもありです。実際私も都市計画法が苦手でかなり捨てました。あとは祈るのみです 出るなー!
過去問の周回回数
あとは理想は全部常識化できるようにとにかく過去問を早く回します。わからなくても悩まずとにかく読んで肢を1つでも多く常識化していきます。私は2週間で4周分ぐらい回しました。常識化数が増えるとどんどん早く回るのでやればやるほどペースが速くなります。
ただ時間がなかったので常識だ!と思える基準は低かったと思います。つまり常識となっていないのに常識化としてチェックを入れている部分も多くありました。あと同じような問題も1つか2つ残して消してしまっていました。また試験日を迎えても常識化されていないものもたくさんありました。間に合いませんでした。ただわからない問題ほど多く触れることになってはいたので仕方ないといったところです。時間があれば横着せずにやっていくと素晴らしい勉強方法だと確信しています。
直前期にやって良かったこと・後悔したこと
やって良かったこと
- 焦りをうまく活用できた
- 過去問をとにかく読んだ(私は2週間で4周ぐらい回しました)
- テキストは寝る前(15分程度)とか会社の行き帰りの電車内で読んでました
後悔したこと
- 始める時期が遅かった
- 常識化されていないのに常識化とした
- 宅建業法が苦手とわかっていたのに注力しなかったこと
今ならこうする
3か月前からしっかり勉強します。(笑)
まとめ|まだ間に合う!行動すれば未来は変わる
合格は「今からどう動くか」で決まる
宅建試験は残り1か月でも合格可能です。大切なのは「過去問にでてくるところだけをする」「過去問を徹底的に読む」という2点です。
今日からできる最初の一歩
- テキスト全力読書
- 直前期に伸ばしやすい宅建業法から取りかかる
- 過去問全力読書
諦めるか、挑戦するか。
本気になれたらまだ間に合います。
よければこちらもどうぞ
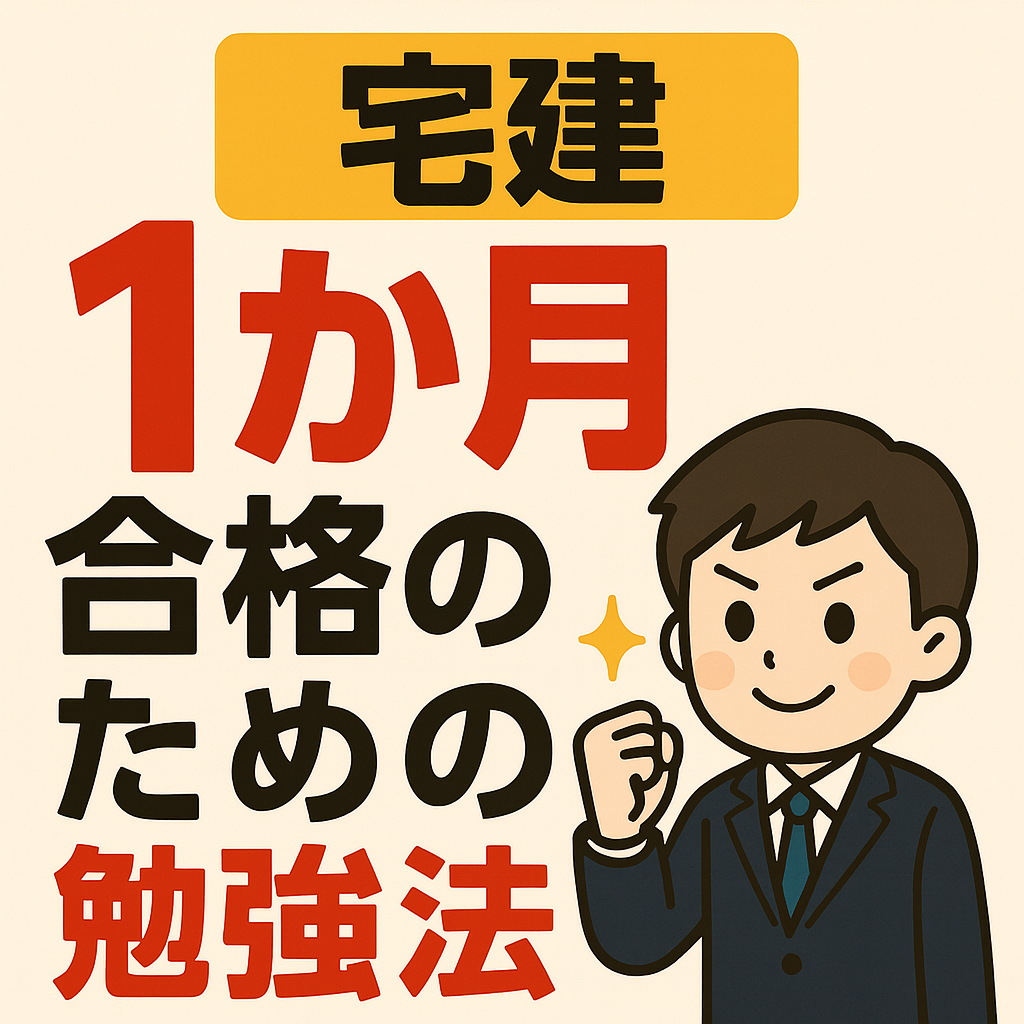

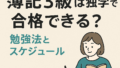
コメント