私が宅建を受験したときの勉強方法についてご紹介します。 私が受験したのは、まだ資格名が「宅地建物取引主任者」の時代(2015年の名称変更前)でしたが、勉強方法に大きな違いはありません。 当時どのように学習したか、どのように勉強すればいいかを解説します。 私は時間が限られていたため短期合格を目指しましたが、そうでない方法も解説します。 用意するものは、テキスト1冊と過去問題集です。 テキストはなんでも構いません。 過去問題集は、左に問題、右に解説が載っている単元別のものが望ましいでしょう。
目次
INPUT期(最初の2日)
この期間は、テキストを3周読みます。 テキストの読み込みで大事な点は2つあります。
- わからなくてもとにかく先に進む 特に最初の1周目は、ほとんどの内容が理解できなくても大丈夫です。1つ1つを完璧に理解しようとすると、いつまでたっても終わりません。学習初期に一番大切なのは、全体像をできるだけ早く把握することです。そのため、1周目は一定のペースで全体をざっと読み切ることに集中しましょう。
- インプット自体は重要ではない ただ本を読んでマーカーを引いているだけでは、勉強した気にはなりますが、学習はほとんど進んでいません。学習が進んだと言えるのは、問題を解けるようになったときです。 問題を解かない限り、問題は解けるようになりません。だからこそ、インプット作業はさっさと終わらせたいのです。
1周目が終わったら、2周目、3周目も同じ要領で読み進めます。気になるところがあれば少しだけ時間をかけてもいいですが、深入りは禁物です。理解できなくても問題ありません。 なぜなら、その部分は試験で出題頻度が低いかもしれませんし、たとえ出題される論点だとしても、どのように問われるかがわかってから覚えた方が効率的だからです。 このように、インプットは短期間で終えることを目標に、サクッと3周読んでしまいましょう。
OUTPUT期(3日目〜試験3日前)
ここからはひたすら過去問題集に取り組みます。この過去問のやり方こそが、合否を左右するといっても過言ではありません。
過去問勉強_初期(3日)
まずは過去問を「読み物」として読み進めます。 問題を読んでわからなければ、すぐに解説を読みましょう。 このとき、過去問の選択肢(肢)ごとに、問題文を読み、すぐに答えと解説を読むことを繰り返します。
なぜなら、過去問は正解を当てること自体が目的ではないからです。選択肢ごとの内容が正しいのか、どこが間違っているのかを説明できるようになる必要があります。「次のうち正しいものはどれか」という問題で、勘で正解しても意味がありません。
このように、まずは深く考えず、読み物として1周早く終わらせましょう。
過去問勉強_中期(6日)
次に、真剣に選択肢ごとに問題を解いていきます。 このとき、選択肢の横に以下のように分類分けしながら解き進めます。
- A: 完全に理解しており、次にこの問題に取り組む必要がない
- B: 正解は出せるが、まだ自信がない
- C: まったくわからない、または間違えた
何度も繰り返してすべての選択肢を【A】にできれば、合格は間違いありません。 ただ、この段階に入ったばかりだと【C】が多くて辛く感じるかもしれません。しかし、この時期の【C】は、過去問を数周回すうちに【B】や【A】に変わることが多いので気にしなくて大丈夫です。
【A】をつけた選択肢は、今後問題を解く必要がありません。私はマジックで問題を塗りつぶして無視していました。 この時期は過去問題集を4周ほど繰り返しました。 必要に応じて、知識の補足や体系的な整理のためにテキストも活用しましょう。
過去問勉強_後期(3日)
過去問を5周ほど回し、この段階でも【C】がついている選択肢は対策が必要です。 まず、出題頻度が低いものや、覚える量が多すぎて今からでは間に合わない【C】は**「捨てる」**と判断しました。 どうせ無理なものや出題されにくい論点を無理に覚えるより、【B】や、対応できそうな【C】を少しでも上のランク(AやB)に引き上げる方が効率的だと考えたからです。
対応策として、【B】や【C】の選択肢は1つ1つテキストに戻って確認したり、紙に書いたり、誰かに説明するイメージで声に出したりしながら、繰り返し知識を定着させました。 試験直前は、完璧ではなくても少しでも理解が進んだものは【A】に格上げしていきました。これは、試験当日に「ほとんどの問題が解ける」という自信をもって臨みたかったからです。
直前期(試験前々日〜試験日)
この2日間は、ほとんど過去問は解きませんでした。 自分の苦手な論点や、これまでに間違えた箇所を中心に、ひたすらテキストを読み込んでいました。 最初に読んだときとずいぶん違って見えたのを覚えています。
まとめ&もっと期間を取った場合の勉強法
私は短期で詰め込む形になり、運も味方して合格できました。ここで言う「運」とは、捨てた論点が出題されなかったことです。 しかし、こんな綱渡りな方法ではなく、もっと期間を取って勉強することをおすすめします。 期間を長くとる場合は、過去問勉強_中期の期間を長くするだけです。インプットに時間をかけすぎるのはやめましょう。
あくまで過去問を解いた上で、確認や周辺知識の補充、体系的な知識整理のためにテキストに戻るようにしてください。
私は、過去問の選択肢をすべて【A】にすることを**「常識化」と呼んで、その進捗をKPI**(Key Performance Indicator:進捗度合いを評価するための指標)として管理していました。これは本来、会社などの組織の業績を管理・評価するための指標ですが、自分の試験勉強の進捗を管理する意味で使っていました。
このように、選択肢のうち【A】が占める割合を計測し、合格に向けて進捗を管理しました。 以上の方法で、私は合格基準点ギリギリで受かりました(ギリギリですが!)。
一冊のテキストと問題集を徹底的にやりこむのが近道です
おすすめテキスト&問題集はこちら↓

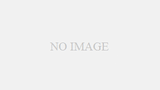
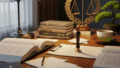
コメント